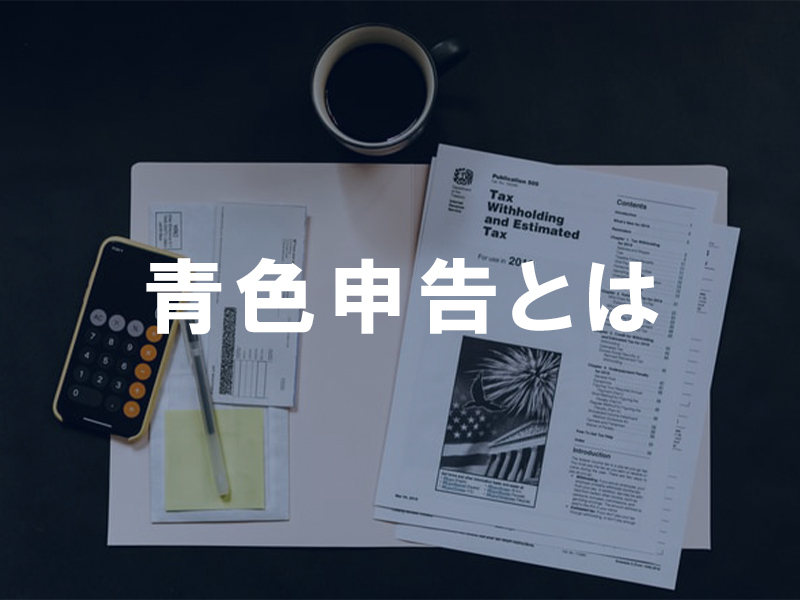こんにちは!ライフアートエージェンシィです!
不動産投資にを始めると必ず必要になるのが確定申告です。
この確定申告には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
この記事では確定申告の青色申告がどのような申告方法なのかを説明した用語解説記事です。
あなたの確定申告にこの記事の内容を役立ててください。
・青色申告について
・青色申告のメリット・デメリット
確定申告とは?
まずは、確定申告が何なのか説明します。
確定申告は、1年間の所得の金額とその所得に対する税金を計算するものです。
次の年の3月15日(通常)までに、申請者の住んでいる管轄の税務署に申告・納税することを確定申告と言います。
不動産所得がある人と、不動産譲渡所得がある人は必ず行わなければなりません。
もしも不動産投資で売却や家賃収入が赤字だったとしても確定申告は必ずしなければいけないので注意しましょう。
申告や納税を怠たったり、遅れたりすると、無申告加算税・延滞税がかかりますので確定申告は期間内に速やかに終わらせられる様にしましょう。
青色申告とは?
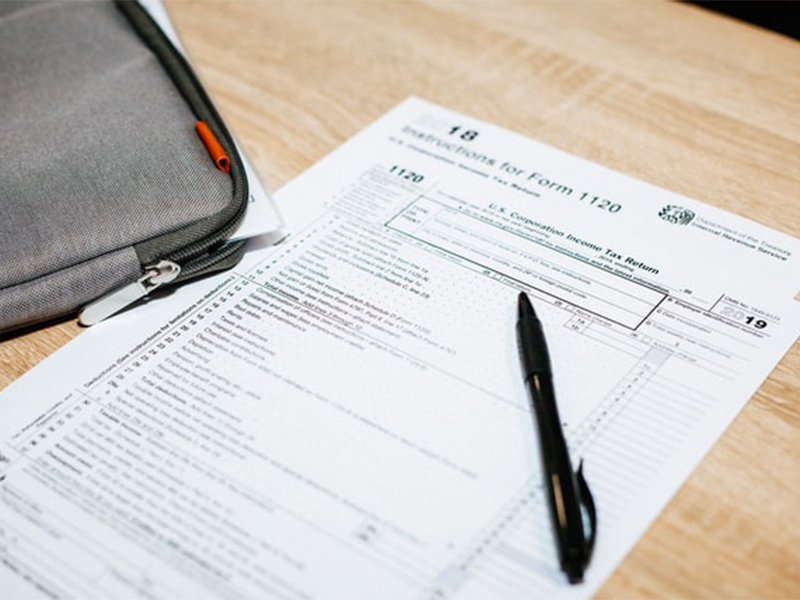
次に青色申告とは何なのかを説明していきます。
青色申告を新規で行うためには、まず管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
提出時期は、青色申告を始める年の3月15日までです。
届け出を忘れてしまうと青色申告ができないので注意してください。
記帳方法
青色申告の場合は、複式簿記での記帳が必須となります。
売上や経費などを複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成しなければいけません。
これらの決算書は、確定申告の際に提出が必要で、帳簿や請求書、領収書は、確定申告書の提出期限日の翌日から、7年間保管をしていなくてはいけません。
貸付け規模
青色申告をすると65万円の特別控除が受けられますが、それは不動産の貸付け規模が事業的規模にあたる場合に限られます。
事業的規模にあたるのは、以下のような場合です。
1. 独立家屋は、概ね5棟以上の貸付け
2. アパートなどは、賃貸が可能な独立した部屋が概ね10室以上
この5棟10室を目安に事業的規模かどうかを判断し、事業的規模にあたる場合は、65万円の青色申告特別控除に加え、専従者給与控除が認められます。
事業的規模でない場合は、専従者給与控除は使えず、青色申告特別控除の額も10万円となりますので目安をおぼえているといいでしょう。
青色申告のメリット・デメリット
次に、青色申告のメリット・デメリットを説明します。
青色申告のメリット
青色申告特別控除(最高65万円)
この特別控除は、青色申告の最大のメリットといえます。
納める所得税が少なくなり、この控除が住民税・国民健康保険料の計算にも反映されます。
控除額には10万円控除(簡易簿記か現金式簡易簿記)と65万円控除(複式簿記)の2種類があります。
白色申告の場合は、この控除の対象にはなれませんので白色申告との大きな差と言えます。
赤字の繰越可能(3年間)
青色申告を選択すれば、赤字になった年の損失の全額を3年に渡って繰り越せるので、翌年以降の節税が可能です。
一方で、白色申告では基本的に赤字の繰越はできません。
家族への給与が経費での処理可能
白色申告の場合は、個人事業を手伝った家族に給料を支払ってもそれを経費計上することはできませんが、青色申告では経費にすることが可能です。
青色申告のデメリット
また、青色申告のデメリットには以下のようなことが挙げられます。
事前に申請が必要
前述しましtが、青色申告を行う場合は、申告年の3月15日までに税務署への申請が必要になります。
そのため、青色申告をしたいと思っても急に変更をすることはできません。
2021年の確定申告で青色申告をしたい場合は2020年の3月15日までに必要です。
正規簿記の原則に従った会計処理が必要
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿を付けなくてはいけません。
複式簿記の記帳は複雑で手間がかかるため、簿記の知識がない人は煩わしく感じるかもしれません。
書類の不備があれば青色申告が取り消されることがある
青色申告で使用する帳簿や領収書、請求書などは7年間保存することが法律で定められており、確定申告後の保存が必要です。
もし税務署からの調査があった際に書類を提示できないと、青色申告の承認が取り消されてしまう場合があるので絶対に捨てずに保管所ましょう。
【青色申告とは?】不動産投資で理解した方がいい確定申告の基本! | まとめ
以上が確定申告の青色申告についての解説でした
青色申告のメリット・デメリットをしっかり検討した上で、記帳・帳簿管理に時間を費やす以上のメリットがあれば白色申告から青色申告の切り替えを進めましょう。
基本的な知識として覚えていると役立ちますので、ぜひ生かしてください!
不動産投資について相談してみたいという方はライフアートエージェンシィにもお気軽にご相談ください。
公式LINEからも相談受け付けています。